戦前・戦後と歌謡界の主流であった音楽学校出身者は昭和30年代に入るとかなり少なくなる。
1946(昭和21)年に、NHK素人のど自慢が始まり、素人が人前で歌を歌う機会が多くなり、歌謡コンクールなどをきっかけとしてデビューする歌手も増えてくる。
浪曲出身の村田英雄、三波春夫、民謡出身の三橋美智也などが歌謡界を引っ張る存在となり、歌声、歌唱法ともにさらに多様化が進む。
また、戦後間もなくデビューした美空ひばりの天性の歌唱・表現力は、後の演歌、ポップスの両分野に影響を与え、彼女は歌謡界の女王として君臨した。
春日八郎 (1924-1991)
1948(昭和23)年、キングレコードのテストに合格。
1952(昭和27)年、江口夜詩作曲の「赤いランプの終列車」がヒット。1954(昭和29)年「お富さん」が大ヒットし、スター歌手となる。
昭和30年代に入り、「別れの一本杉」「あン時ゃどしゃ降り」「山の吊橋」などを次々にヒットさせる。低音域はやや魅力に欠けるが、ピーンと張りのある高音とバイブレーションを利かせた独特の節まわしで、演歌調の曲では第一人者となり、三橋美智也と共に昭和30年代の歌謡界を引っ張った。
美空ひばり (1937-1989)
1949(昭和24)年、松竹映画「踊る竜宮城」の主題歌「河童ブギ」でデビュー。同年、映画「悲しき口笛」に主演し、同名の主題歌も歌いヒットさせる。
さらに、1950(昭和25)年「東京キッド」、1951(昭和26)年「私は街の子」「あの丘越えて」、1952(昭和27)年「リンゴ追分」「お祭りマンボ」と映画に歌に大活躍、『天才少女』の名を欲しいままにする。
昭和30年代に入っても「港町十三番地」「花笠道中」「哀愁波止場」「柔」などを、昭和40年代には「悲しい酒」「真赤な太陽」などをヒットさせる。ドスの利いた低音からファルセットを巧みに使った高音まで非常に音域が広く、正確な音程と天性のリズム感で「歌謡界の女王」の座に君臨する。
晩年のヒット曲としては「愛燦燦」「川の流れのように」などの名曲がある。1989(平成元)年に亡くなり、死後、国民栄誉賞が贈られた。
若原一郎 (1931-1990)
1949(昭和24)年、NHKのど自慢全国コンクールで3位に入賞し、キングレコードの専属となる。
しばらくヒットに恵まれなかったが、1954(昭和29)年「吹けば飛ぶよな」がヒットし、第一線に躍り出る。明るく伸びのある美声と軽い歌い方で、1956(昭和31)年「山陰の道」、1957(昭和32)年「丘にのぼりて」、1958(昭和33)年「おーい中村君」と次々ヒットを出す。
青木光一 (1926-)
戦時中は、満州・奉天で放送合唱団員として活躍するが、終戦後、シベリアに抑留される。
1949(昭和24)年、シベリアから帰還し、合唱団時代の師・作曲家米山正夫の紹介でコロムビア入りし、1950(昭和25)年、「燦めくスバル」でデビュー。
1953(昭和28)年、「元気でね、左様なら」が初ヒット。艶のある低音と張りのある高音で、「小島通いの郵便船」「早く帰ってコ」「柿の木坂の家」などふるさとの郷愁溢れる歌を数多くヒットさせる。
1983年に日本歌手協会の理事就任、 2007年から同名誉会長。
若山彰 (1927-1998)
武蔵野音楽大学を卒業後、1951(昭和26)年、コロムビアからデビュー。
しばらくヒット曲に恵まれなかったが、1957(昭和32)年、松竹映画の主題歌「喜びも悲しみも幾年月」が大ヒットとなる。
いくぶん暗みがかった重厚な歌声とクラシックを基礎とした歌唱法で、「惜春鳥」「二人で歩いた幾春秋」などをヒットさせる。巨人軍応援歌「闘魂込めて」やタイガース応援歌「六甲おろし」なども歌っている。
1989(平成元)年、脳梗塞に倒れるがリハビリの末復帰した。
三浦洸一 (1928-)
神奈川県三浦のお寺の三男として生まれる。
東洋音楽学校卒業後、1953(昭和28)年にビクターから「さすらいの恋唄」でデビュー。続いて出した「落葉しぐれ」が大ヒット。
低音から高音まで快く響く歌声と、折り目正しい楷書的な歌唱法で、「弁天小僧」のような手拍子ソングや「東京の人」「ああダムの町」「街燈」など吉田正作曲による都会的ムード漂う曲を多くヒットさせる。1957(昭和32)年には「踊子」をヒットさせ、文学作品の歌謡化に成功したのも、その歌唱の格調高さに依るところが大きい。
[PR] おすすめCD
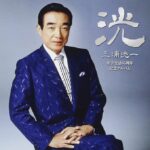 三浦洸一 歌手生活65周年記念アルバム~洸~(Victor)
三浦洸一 歌手生活65周年記念アルバム~洸~(Victor)歌手デビュー65周年記念アルバム。吉田正門下生の最上級生でビクターの伝説的ヒット歌手。「落葉しぐれ」「踊子」「街燈」などの大ヒット曲7曲+初CD化音源10曲+カラオケ4曲が収録され、カラオケで歌いたい人にはおすすめ。そして90歳当時の本人メッセージを収録。
藤島桓夫 (1927-1994)
大阪で電話局に務めるかたわら、歌謡学院で歌のレッスンを受ける。1950(昭和25)年、タイヘイ(タイヘイ音響)から「ああ東京へ汽車は行く」でデビュー。
鼻にかかった独特の歌声と丁寧な演歌調の歌唱で、1954(昭和29)年「初めてきた港」、1955(昭和30)年「かえりの港」とヒット。さらに、1957(昭和32)年には「お月さん今晩は」が大ヒット。
東芝レコードへ移籍後、1960(昭和35)年、「月の法善寺横丁」をヒットさせ、大阪物はヒットしないというジンクスを吹き飛ばした。
織井茂子 (1926-1996)
少女時代から童謡歌手として活躍。大村能章の日本歌謡学院で学び、キングレコードから都能子の名でデビュー。 ヒットに恵まれなかったが、林伊佐緒の紹介でコロムビアに移り、1953(昭和28)年、松竹映画「君の名は」の主題歌「君の名は」「黒百合の歌」が大ヒットとなる。混じり気のないアルトの美声と力強く、かつ、正確な歌唱で息長く活躍した。
菅原都々子 (1927-)
父親は元浅草オペラの歌手、作曲家の陸奥明。古賀政男の養女となり、1937(昭和12)年、古賀久子の名で童謡歌手としてデビュー。
1940(昭和15)年から本名の菅原都々子になり、「乙女馬子唄」「アリラン月夜」などをヒットさせる。
強烈なヴィブラートのかかった独特の歌唱法で、1951(昭和26)年「江の島悲歌」「連絡船の唄」をヒットさせ『哀調の歌姫』と呼ばれる。同年の1月3日放送、第1回「NHK紅白歌合戦」にて記念すべき第1号出演者として「憧れの住む町」を歌唱。
1955(昭和30)年には、陸奥明作曲による「月がとっても青いから」が大ヒット。
(初代)コロムビア・ローズ (1933-)
1951(昭和26)年、コロムビア全国歌謡コンクールで優勝。1952(昭和27)年、覆面歌手として「娘十九はまだ純情よ」でデビューする。
澄んだ歌声と哀愁を漂わせた丁寧な歌い方で、「渡り鳥いつ帰る」「どうせひろった恋だもの」「東京のバスガール」などをヒットさせる。1962(昭和37)年、結婚し引退する。
越路吹雪 (1924-1980)
長野県飯山高等女学校を卒業後、宝塚歌劇団に入る。
1949(昭和24)年、コロムビアから「ブギウギ巴里」でレコードデビュー。1950(昭和25)年、ポリドールから「ビギン・ザ・ビギン」を出す。
1951(昭和26)年に宝塚歌劇を退団。
その後、東芝レコードに移り、1961(昭和36)年「ラストダンスは私に」、1964(昭和39)年「サム・トワ・マミー」などをヒットさせる。
その他、「愛の賛歌」などシャンソンの名曲を聴衆に訴えかけるようなダイナミックな歌唱で歌う。そのステージは聴く者を引き付け、カリスマ的存在として一時代を築いた。
江利チエミ (1937-1982)
1951(昭和26)年、キングレコードのオーディションに合格し、アメリカでヒットしていたテネシーワルツを日本語で歌い、ヒットさせる。
ダイナミックな歌唱と明るいキャラクターで人気を得て、美空ひばり、雪村いづみとともに『三人娘』と呼ばれる。アメリカでカール・ジョーンズに師事し、ジャズシンガーとしてスターの地位を確立。その後、女優としても活躍するが、1982(昭和57)年、脳卒中と吐瀉物が気管に詰まっての窒息で突然の死去。
雪村いづみ (1937- )
父親の自殺もあり、10歳の頃から進駐軍のキャンプ巡りをして生計を立てる。
日劇ミュージックホール出演中にスカウトされ、1953(昭和28)年、ビクターから「想い出のワルツ」でデビュー。
抜群のリズム感と歌唱力で、1954(昭和29)年「青いカナリア」「オー・マイ・パパ」、1956(昭和31)年「慕情」「エデンの東」などのジャズソングを歌い、ヒットさせる。
また、1977(昭和52)年にはミュージカル「マイ・フェア・レディ」にも出演。
三橋美智也 (1930-1996)
子供の頃から母親に民謡を教わり、11歳の時、北海道の民謡コンクールで優勝し、『民謡界の少年横綱』と呼ばれる。また、三味線を鎌田蓮道に、津軽三味線を白川軍八郎に学ぶ。
1953(昭和28)年、キングレコードにスカウトされ、翌年デビュー。1955(昭和30)年、「おんな船頭唄」が大ヒットとなる。
民謡を基礎にした節回しと張りのある高音の魅力で、「リンゴ村から」「哀愁列車」「おさげと花と地蔵さんと」「夕焼けとんび」「達者でな」「古城」と立て続けにヒットさせ、『ミッチーブーム』を巻き起こす。その後も、歌謡界の第一人者として、また、民謡では三橋流の家元として幅広く活躍する。
曽根史郎 (1930-)
1954(昭和29)年、ポリドールから「雪之上変化の唄」でデビュー。1956(昭和31)年、「若いお巡りさん」が大ヒット。
快く響く明るい歌声とお巡りさんのスタイルで、米寿を迎えてもなお現役で歌手活動を続けている。他に「帰る故郷もない俺さ」などのヒットがある。
松山恵子 (1938-2006)
1954(昭和29)年、マーキュリーレコードの全国歌謡コンクールで優勝し、翌1955(昭和30)年「マドロス娘」でデビュー。
1956(昭和31)年「十九の浮草」で初ヒットを飛ばし、1957(昭和32)年「未練の波止場」、1958(昭和33)年「だから云ったじゃないの」と続けてヒット。
1959(昭和34)年、東芝レコードへ移籍後も、バイブレーションを効かした独特の歌い回しで、「お別れ公衆電話」をヒットさせる。
豪華なステージ衣装と右手に持ったハンカチはトレードマーク。『お恵ちゃん』の愛称で親しまれ、少女のようなかわいらしさで幅広いファンに親しまれた。
島倉千代子 (1938-2013)
1954(昭和29)年、コロムビア全国歌謡コンクールに優勝して、コロムビアと契約。1955(昭和30)年、「この世の花」でデビュー。
同年「りんどう峠」、1956(昭和31)年「東京の人さようなら」、1957(昭和32)年「東京だよおっ母さん」、1958(昭和33)年「思い出さん今日は」「からたち日記」と立て続けにヒットを出す。
澄んだ歌声とささやきかけるような歌い方で、1961(昭和36)年「襟裳岬」「恋しているんだもん」、1966(昭和41)年「ほん気かしら」などがヒット。
美空ひばりとは対照的な心を込めた丁寧な歌唱で女性トップ演歌歌手となる。1981(昭和56)年には「鳳仙花」、1987(昭和62)年には「人生いろいろ」をヒットさせ健在ぶりを見せた。
2014年のデビュー60周年に向け、死去3日前の2013年11月5日に自宅で記念曲『からたちの小径』を録音、遺作となった。
フランク永井 (1932-2008)
1955(昭和30)年、ビクターから「恋人よわれに帰れ」でデビュー。
初めはジャズを歌っていたが、その魅惑的な低音の歌声を吉田正に認められ、歌謡曲を歌うようになる。
1956(昭和31)年「公園の手品師」、1957(昭和32)年「東京午前3時」「夜霧の第二国道」「有楽町で逢いましょう」、1958(昭和33)年「羽田発7時50分」「西銀座駅前」、1959(昭和34)年「夜霧に消えたチャコ」と次々ヒットを飛ばし、ムード歌謡の先駆者的存在となる。
さらには1929(昭和4)年に発売された「君恋し」をムード歌謡的にリバイバルし、ヒットさせる。他に「霧子のタンゴ」「逢いたくて」「おまえに」などのヒットがある。
1985(昭和60)年、自宅で自殺を図り、命は取りとめたものの再起不能となる。
三船浩 (1929-2005)
1949(昭和24)年、NHK全国歌謡コンクールで3位に入賞。キングレコードから1956(昭和31)年にデビュー、「男のブルース」が大ヒットとなる。
豊かな低音の歌声とスケールの大きな歌唱で、「夜霧の滑走路」「俺は男というサムライさ」などのヒットがある。また、「月光仮面」などのテレビ主題歌も歌っている。
三波春夫 (1923-2001)
16歳で日本浪曲学校に入学。南篠文若の名で浪曲歌手としてデビューする。1957(昭和32)年、歌謡界に転向し、三波春夫の名でデビュー。
浪曲調の歌声を歌謡曲向きの伸びのある明るい歌声に変え、「チャンチキおけさ」「船方さんよ」「雪の渡り鳥」「東京五輪音頭」と次々ヒットを飛ばす。また、「鴛鴦道中」「大利根無情」など股旅ソングのヒットも多い。70歳を越えても、明るく朗々とした歌声は変わらず、レオタード姿の女性をバックダンサーに従えるなど、伝統的な浪曲調に現代的感覚を取り入れた独特の芸風をもっていた。
村田英雄 (1929-2002)
浪曲師の家に生まれ、4歳のときに初舞台を踏む。酒井雲坊の名で浪曲師として活躍。
1951(昭和26)年、上京し、翌1952(昭和27)年、浪曲新人最優秀賞、1953(昭和28)年、桃中軒雲右衛門賞を獲得。古賀政男にスカウトされ、1958(昭和33)年コロムビアから村田英雄の名でデビュー。
浪曲を基礎としたドスの効いた男らしい歌っぷりで「無法松の一生」が大ヒット。1959(昭和34)年には、戦前に楠木繁夫が吹き込んだ「人生劇場」を歌い、ヒットさせる。1961(昭和36)年には「王将」がミリオンセラーとなる。その後も「皆の衆」などのヒット出す。
近年は、相次ぐ闘病生活、脱疽による片足切断などの不幸に見舞われるが、不屈の闘志で奇跡の復活を果たした。
二葉百合子 (1931-)
浪曲師・東若武蔵を父にもち、4歳で初舞台を踏む。9歳でポリドールからレコードを出し、天才少女と呼ばれた。
戦後は歌謡浪曲の分野を開拓。1975(昭和50)年には、戦後まもなく菊池章子が歌った「岸壁の母」をリバイバルで吹き込む。浪曲調の歌い回しと情感たっぷりに語りかける台詞入りで大ヒットとなる。
2010年、現役引退し、77年間の芸能生活に終止符。日本浪曲協会名誉顧問として後進を育成。
2023年11月4日、BS朝日「人生、歌がある」で「岸壁の母」を熱唱、92歳歌声健在。
白根一男 (1937-)
1953(昭和28)年、テイチクの新人コンテストに優勝し、「夜霧の酒場」でデビュー。
1955(昭和30)年、「次男坊鴉」が大ヒットし、スター歌手仲間入り。渋い低音の美声で女性ファンの人気を集める。1961(昭和36)年に出した「はたちの詩集」など、台詞入りのヒット曲が多い。
最近も新曲を発売するなど精力的に活動中。
大津美子 (1938-)
渡久地政信に師事し、1955(昭和30)年、キングレコードから「千鳥のブルース」でデビュー。続く「東京アンナ」が大ヒット。
1956(昭和31)年には「ここに幸あり」、1958(昭和33)年には「銀座の蝶」をヒットさせる。
力強いアルトの歌声とダイナミックな歌唱で活躍する。
1980(昭和55)年、クモ膜下出血に倒れ、生死の境をさまようが、奇跡的にカムバック。現在も力強いその歌声は健在。
神戸一郎 (1938-2014)
1957(昭和32)年、コロムビアから「十代の恋よさようなら」でデビュー、ヒット曲となる。
翌年、「銀座九丁目は水の上」がヒット。温かみのある低音の歌声、スリムな体型と甘いマスクでアイドル的存在となる。
松尾和子 (1935-1992)
中学卒業後上京し、進駐軍のキャンプでジャズなどを歌う。
赤坂のクラブ・リキの専属歌手として歌っていたところをフランク永井にスカウトされ、1959(昭和34)年、ビクターからフランク永井とのデュエット「東京ナイトクラブ」でデビュー。
1960(昭和35)年の「誰よりも君を愛す」は大ヒットし、日本レコード大賞を受賞。甘く官能的な歌声で、1960(昭和35)年には「再会」もヒットさせている。
1992(平成4)年、自宅の階段から落ちる事故が原因で亡くなった。
@伊藤家の書斎



























情報提供・コメント